問題の種類
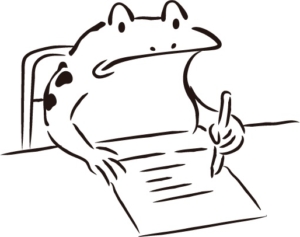
問題は3タイプ
- 知ってたら解ける問題
- 解き方を覚えたら解ける問題
- 読んだらわかる問題
どのタイプの問題かを見極めよう
入試本番はもちろんのこと、模試や過去問演習などでは、今解いている問題がどのタイプの問題なのかを見極めることが大切です。それによって、「解けないとき」の対応が変わるからです
知ってたら解ける問題、への対応
いわゆる「知識問題」です
このタイプの問題は「思い出せるか」「そもそも知っているか」が重要。入試本番中、できなければ、いくら考えたところで出てこないので「すぐ飛ばす」。学習中の場合は、演習後、必要な知識を確認するだけでいいものです
このタイプの問題に「難しさ」はゼロです
「解けなかった問題」を「難しい」と言う人もいますが、間違いです。知っていれば解ける。知らなければ解けない。ただそれだけです。「難しい」という言葉はなるべく使わないようにしましょう。それだけで、「暗記」がとてもしにくくなります
知識は「忘れる」ことを前提に学習
「忘れる」のは、脳が正常に働いている証拠です。何も悪いことではありません。忘れることは当たり前なことなのです。なので、できた・できなかったはあまり気にせず、忘れるたびに、正しい知識を確認しましょう。それを繰り返していくうちに、だんだん問題が解けるようになってきます
解き方を覚えたら解ける問題、への対応
これは知っていても解けない
その知識の使い方が重要で、「道具の使い方」に似たところがあります。金づちがどういうものかを知っていても、使うにはある程度の練習が必要なのと同じです
練習の方法はシンプルで①公式を覚える、②公式を使って問題を解く
特に②の公式を使って問題を解く、をたくさん行うことです
で、どのくらいを目標に練習すればいいかというと、「公式を意識せず使えるようになるまで」
公式を「思い出す」作業をせずに解けるようになればOKです。大工さんがいちいち金づちの使い方を確認しないのと同じですね
読んだらわかる問題、への対応
問題を読むと意味不明
知らない、よくわからない言葉が並んでいる。解いたことのないような問題だとすると、それは「読んだらわかる問題」です。特に難関校では、この「読んだらわかる問題」がよく出てきます
これは文字通り、読んだらわかります
試されている能力は「新しい知識に対する柔軟な対応」です。見た目の難しさに騙されないようにしましょう
こればかりは、経験値が必要
とにかく数多くの過去問に取り組みましょう
読んだらわかる問題だな、と判断したらとにかく読む
あとは基本的な知識との組み合わせと、「やれと書いてある通りにやる」ことが大切です。こういう問題は得意不得意もあったりするのですが、こつはとにかく「失敗を恐れず取り組んでみよう」です
この問題の特徴は、答えを出すために必要な情報はすべて「書いてある」ということです
とにかく読んで、しっかり対応しましょう
過去問は最高の学習ツール
受験勉強は、どれだけ早く過去問に取り組めるかがカギになります
過去問に取り組むときは、今取り組んでいる問題がどのタイプの問題なのかを判断し、問題タイプに合わせた対応をしてみましょう。特に「読んだらわかる問題」は、解けるようになると他の受験生と圧倒的な差をつけることができるようになります。ぜひ、チャレンジしましょう
一人一人に最高の学習指導を
>>お問合せはこちらから

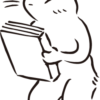

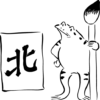


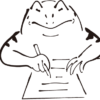
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません