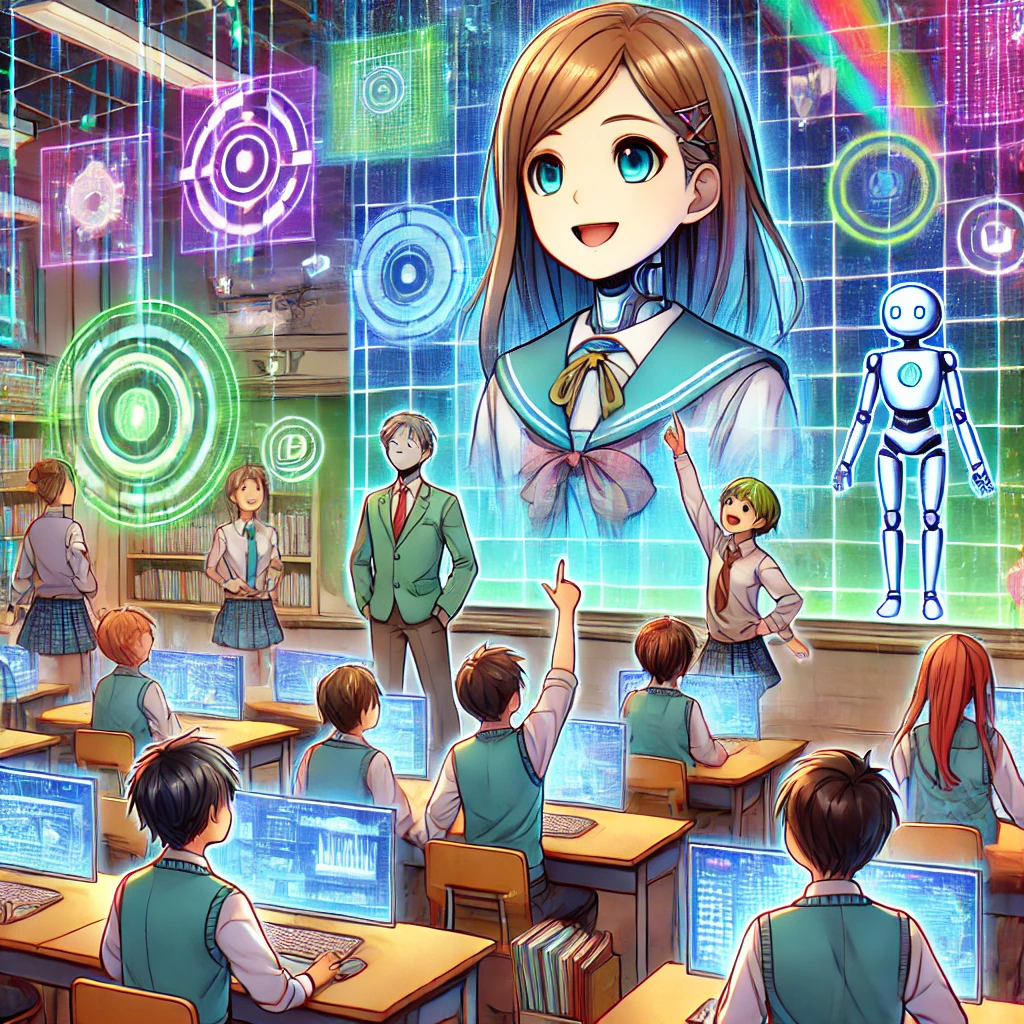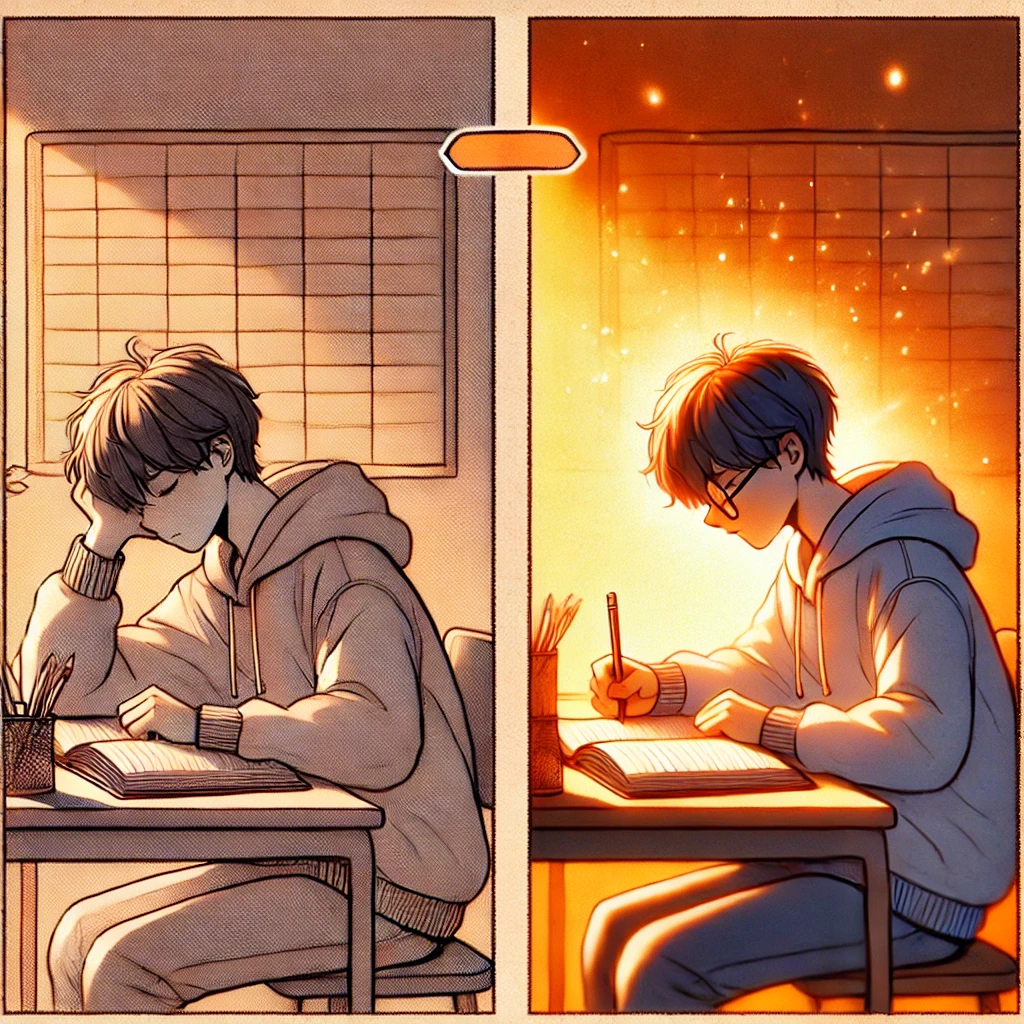勉強嫌いは「強制」から生まれる理由
子どもが勉強嫌いになる最大の原因は、「強制」です。どんなに好きだったことでも、無理やりやらされると嫌いになってしまうことがあります。本記事では、親ができることとして「選択肢を与えること」と「邪魔をすること」に注目し、勉強を嫌いにさせない工夫を紹介します。さらに、デジタル機器の影響や、実際の家庭でのルールを例に挙げながら、具体的な対策を提案します。
- 好きなことに理由はない
- 嫌いなことには理由があることが多い
- 好きなことも、「親の介入」しだいでは嫌いになることも
- ご褒美には要注意(また別記事で紹介しますが、好きでやっていることにご褒美をあげると、「報酬」」が動機となり、自発性が失われます)
勉強嫌いにさせないために親ができること
「勉強を好きにさせる方法」はありませんが、勉強を嫌いにさせないための工夫はできます。そのために、親ができることは次の2つです。
1. 子どもに選択肢を与える
親は、子どもに勉強の選択肢を与えることができます。たとえば、本を与える、教材を用意する、興味を持ちそうな学習環境を整えるなどです。しかし、それを「やるかどうか」は子ども次第です。無理に押し付けるのではなく、興味を引く環境を整えることが大切です。
2. 子どもの自発性を尊重するために「邪魔をしない」
少し厳しいお話になりますが、親の介入は子どもの自発的な行動を、原則抑制する方向に働きます。子ども自発性を育てるためには、「子どものやりたいこと」をさせることが重要です。
もちろん、特に小さな子どもには「善悪」などの判断が難しいところがあります。いいことはやっていいけど、わるいことはやってはいけない、という意味で、子どものやってはいけないことへの介入はある程度行う必要があります。(ただし、消極的に)
何かをさせようとする親の子どもへの介入は
・今、子どもが自発的にしようとしていることを邪魔している
・今、したくないことを強制させている
と、2つの意味で悪影響を与えます
・読んでほしい本があったときに、それを目の前に置いたり、ちょっとお勧めすることは親ができること。
・でもその本を読ませようとするのは「強制」。読む・読まないを選ぶのはあくまで子どもにあり、強制すると「本嫌い」になる可能性があります。結果、それが「本を読むことの邪魔」」になったり、ほかに子どもがしようとしていたことの「邪魔」になったりしています
子どもの学習へ積極的にかかわるなら
- 親はあくまで受け身の姿勢を保つことが大切
- 子どもが「手助けしてほしい」と言ったときに初めてサポートする
- 例えば、本を読んでほしいと言われて、初めて本を読む
- 家事が大変なのは重々承知していますが、子どものことが後回しになっていませんか?チャンスを逃しています
デジタル機器と学習環境の影響
スマートフォンやタブレット、ゲーム機、YouTubeなどのネット動画は、子どもにとって非常に魅力的な存在です。これらは刺激が強く、一度始めるとなかなかやめられなくなってしまいます。そのため、あらかじめ制限を設け、子どもが勉強の時間に集中できる環境を整えることが重要です。
ただし、漫画や読書などは制限せずに楽しめるようにすることも一つの方法です。親が何を制限し、何を許可するかを明確にすることで、子どもも納得感を持ってルールを守ることができます。
勉強を「嫌いにさせない」ことが大切
成長すれば、「好きじゃないけど、やる必要があるからやる」という考え方ができるようになります。しかし、その時に「勉強が嫌い」になっていたら、やはりできなくなってしまいます。そのため、まずは勉強を「嫌いにさせない」ことを意識しましょう。
そのためには、「やりなさい」と強制せず、自然に勉強が生活の一部として受け入れられるような環境作りが大切です。
実際の家庭でのルール例
参考までに、我が家のルールをご紹介します。
- テレビはそもそも置いていない
- ゲームは土曜のみ
- 夜寝る時間が遅くなると、次のゲームの日がなくなる
- こっそりゲームをした場合、1か月禁止
- ルールは厳格に守る
- 一度ルールを破ると、ズルズルと崩れてしまう
- 親の「まぁいいか」という甘さが、結局子どもの学習習慣を乱してしまう
- 子どもは「策士」。このくらいならルールを破っても大丈夫、こう言えばルールをうまくすり抜けられる、ということには天才的なひらめきを発揮します
このように、デジタル機器の影響を抑えつつ、親が一貫性を持ってルールを運用することが重要です。ただし、これはあくまで一例ですので、各家庭の状況に応じてルールをぜひ工夫してみてください。
この記事のまとめと親が意識すべきこと
- 勉強嫌いの原因は「強制」
- 親ができるのは「選択肢を与えること」と「邪魔をすること」
特に子どものためと思ってやっていることが、「実は子どもの邪魔になっていないか」と反省することが大切です - デジタル機器は強い誘惑があるため、制限が必要
- 勉強を「好きにさせる」ことは難しいが、「嫌いにさせない」ことはできる
「強制しない」が原則 - 成長とともに「やる必要があること」に向き合えるようになるため、今は嫌いにさせない工夫が大切
親の関わり方次第で、子どもの学習への向き合い方は大きく変わります。無理に「勉強させる」のではなく、「勉強を嫌いにさせない」環境づくりを意識してみてください。